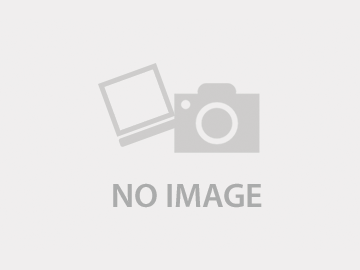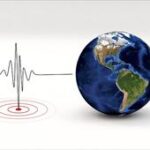人生の節目に訪れる厄年という言葉に、なんとなく背筋がゾワッとする方も多いでしょう。昇進や結婚、出産など嬉しい出来事の一方で、体調不良や予期せぬトラブルが起こることもあるのが厄年です。
古くから、日本では厄除け(厄払い)をして災いを遠ざける習慣があります。
「厄年ってそもそも何?」「なぜ厄除けが必要なの?」――そんな疑問を持つ方に向けて、名古屋で厄除けをする前に知っておきたい基礎知識をご紹介します。
厄年とは何か
厄年とは、一生の中で病気やケガ、災難に遭いやすいとされる年齢のことです。科学的な証明はありませんが、長い歴史の中で人々が気をつけたほうがいいと経験的に感じてきた年齢と言えます。
男女で年齢が異なり、多くの場合、人生の転機や体調の変化と重なります。昔は今よりも平均寿命が短く、心身に負担がかかる時期として意識されてきました。
厄年の数え方
厄年は、生まれた年を1歳とする「数え年」で計算します。お正月ごとに1歳年を取るため、「去年まではセーフだったのに、気づいたら厄年突入!」なんてこともあります。
特に注意が必要なのは「本厄」と、その前後の「前厄」「後厄」。この3年間は要注意期間として、多くの方が厄除けに訪れます。
男女別 厄年早見表
自分の厄年を知りたい方は、以下の表を参考にしてください。
※地域や神社によって異なる場合があるため、参拝予定の神社で確認するのがおすすめです。
| 区分 | 男性(数え年) | 女性(数え年) |
|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 / 41歳 / 60歳 | 18歳 / 32歳 / 36歳 / 60歳 |
| 本厄 | 25歳 / 42歳 / 61歳 | 19歳 / 33歳 / 37歳 / 61歳 |
| 後厄 | 26歳 / 43歳 / 62歳 | 20歳 / 34歳 / 38歳 / 62歳 |
なぜ厄除けが必要なのか
厄除けは災いを未然に防ぐための神聖な儀式です。厄災をもたらすとされる邪気や悪霊を、神様のご加護で祓い清めてもらえます。
もちろん、科学的に邪気が見えるわけではありませんが、厄除けを受けることで心が軽くなり、これで安心!という精神的なお守りを手にできます。
ある意味、厄除けは“心のリセットボタン”ともいえる存在です。
厄除けに行く時期
厄除けは一年中受けられますが、一般的には年明けから節分(2月3日頃)までが人気です。
ただし、この時期は神社が大変混雑します。人混みが苦手な方は、あえて時期をずらすのも一案です。
「厄は気づいたときに祓えばいい」という考え方もあるため、自分の都合や気持ちのタイミングに合わせて参拝しましょう。
厄除けで有名な名古屋の神社3選
名古屋には、古くから人々に愛されてきた由緒正しい神社が数多くあります。
厄年を迎えて「どこで厄払いを受けたらいいんだろう…」と悩んでいる方も多いでしょう。
ここでは、厄除けで特に有名な神社を3つご紹介します。ご利益や雰囲気、アクセスなどを比較して、自分に合った神社を見つける参考にしてください。
格式と安心感の「熱田神宮」
名古屋で厄除けと言えば、まず名前が挙がるのが熱田神宮です。三種の神器の一つ「草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)」を祀る、日本屈指の格式ある神社。
厄除けのご祈祷は、荘厳な雰囲気の中で行われ、気持ちも背筋もピシッと伸びます(猫背の方にもおすすめかもしれません)。
初詣や七五三などでも多くの人が訪れ、特別な安心感を与えてくれる場所です。厄年をしっかり乗り越えたい方にはぴったり。
| アクセス | 地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町駅」徒歩7分 / 名鉄本線「神宮前駅」徒歩3分 |
|---|---|
| 初穂料 | 6,000円〜 |
厄除けと同時にご利益いろいろ「山田天満宮」
山田天満宮は、厄除けに加えて学問や金運アップも同時に願える欲張り派に人気の神社です。
主祭神は学問の神様・菅原道真公。受験生なら「厄払いのついでに合格祈願も」という一石二鳥も可能です。
境内の御嶽神社では金運のご利益があるとされる「銭洗い」も体験できます。財布が軽くなるのは洗ったせいか、運が舞い込む前触れかはあなた次第です。
| アクセス | 地下鉄名城線「大曽根駅」徒歩10分 |
|---|---|
| 初穂料 | 6,000円〜 |
静かに厄を祓う「甚目寺観音」
名古屋市外ですが、名古屋駅から電車で約10分という近さ。約1400年の歴史を持つ古刹で、静かに厄除けを受けたい方におすすめです。
境内は落ち着いた雰囲気で、都会の喧騒から離れて自分と向き合えます。ここでの厄払いは、まるで心の大掃除。埃だけでなく厄もスッキリ落とせます。
開運のご利益もあり、ゆったりした気持ちで新しい一年を迎えたい人にぴったりです。
| アクセス | 名鉄津島線「甚目寺駅」徒歩5分 |
|---|---|
| 初穂料 | 5,000円〜 |
厄除けご祈祷 当日の流れと作法
「厄除け行こう!」と決めたものの、当日の流れや服装が分からないと不安ですよね。ここでは一般的な準備やマナーをご紹介します。
厄除け当日までの準備
まずは参拝予定の神社公式サイトで受付時間や予約の有無を確認しましょう。
初穂料は紅白蝶結びののし袋に入れ、「初穂料」または「御玉串料」と表書きします。お札は新札で、肖像が上向きになるように。
当日の流れ
- 神社に着いたら受付へ
- 住所・氏名・年齢・願い事を記入
- 初穂料とともに提出
- 4待合室で待機
- 社殿に入り、祝詞を受ける
- お守りや撤饌を受け取って終了
服装と持ち物
正装は不要ですが、清潔感のある服装を心がけましょう。
男性はスーツやジャケット、女性は落ち着いた色のワンピースやスカートが無難です。Tシャツやサンダル、露出の多い服は避けましょう。
持ち物は、のし袋に入れた初穂料と、お守りを持ち帰る袋程度でOK。
なお、神社では仏教の念珠は不要です。間違えて持っていくと、神様に「そっちじゃないよ」とツッコまれるかもしれません。
厄払い後のお守りと過ごし方
厄除けのご祈祷を終えたら、それで全て完了…ではありません。
ご利益をしっかり受け取り、厄年を平穏に過ごすためには、その後の過ごし方やお守りの扱い方も大切です。
ここでは、厄払い後に心がけたいことや、お守りの正しい扱い方をご紹介します。新しい一年を清々しく迎えるため、自らも開運の道を選びましょう。
厄払い後のお守りの扱い方
ご祈祷後、神社から授与されるお守りや縁起物は、神様の力が宿る大切な存在です。
ご利益を最大限に受けるためには、肌身離さず持ち歩くのがおすすめ。財布やカバンなど、常に身近な場所に入れておくと安心です。
「置きっぱなし」ではなく「持ち歩きっぱなし」が基本、ただし洗濯機に一緒に入れないように注意です。
自宅に置く場合は、神棚や目線より高い清浄な場所へ。粗末に扱わず、感謝の気持ちを持ちましょう。
お守りは通常一年間使用し、年末か年始に古札納所へ返納してお焚き上げをしてもらいます。これも「ありがとう」の気持ちを神様に届ける大切な儀式です。
厄年に心がけること
厄除けは心の平穏をもたらしてくれますが、それだけで全てが解決するわけではありません。
ご利益を高めるためには、日々の過ごし方にも注意が必要です。
- 新しい挑戦はいつもより慎重に
- 体調管理をしっかり行い健康第一
- 無理をせず、心と体に向き合う
- 感謝の気持ちを忘れず、人への配慮を心がける
厄年は災難を避けるだけでなく、自ら幸運を引き寄せる行動が鍵。
受け身ではなく「自分から開運するぞ!」という姿勢で過ごしましょう。
まとめ
名古屋には、熱田神宮、山田天満宮、甚目寺観音など、特色豊かな厄除けスポットがあります。
神社選びの際は、ご利益や雰囲気、アクセスを比較し、自分の願いや好みに合った場所を選びましょう。
当日は公式サイトで受付時間や予約の有無を確認し、初穂料をのし袋に入れ、清潔感ある服装で参拝することが大切です。
厄除けは、不安を和らげ、心穏やかな一年を迎えるための大切な行事。この記事が、名古屋での厄除けを考えているあなたの参考になれば幸いです。